小習が終わると四ヶ伝の稽古に入ります。
唐物などもそうですが覚えることが多くて困りませんか。

しかでん?とうふう?

からものって読むんだよ♪
点前自体は、身体が覚えているのか自然と動くことがあります。
しかし、点前の準備やポイントを知っていなければ頭が真っ白になってしまうことも少なくありません。
そこで今回は、四ヶ伝の唐物(風炉)の準備や点前のポイントについてまとめました。
【四ヶ伝】唐物(風炉)の準備
四ヶ伝の1つである唐物(風炉)で準備するものは主に6つあります。
【準備するもの】
- 曲水指
- 唐物茶入
- 楽茶碗
- 茶杓(元節)
- 唐金建水
- 柄杓
稽古場の状況にもよりますが、曲水指は事前に濡らしておきます。
私が通ってた稽古場では、濡れたタオルを曲水指に巻いていました。
タオルは点前の直前で外して水指を使っていましたよ。
そのため、使った後は特にしっかりと乾かす必要があります。
また、唐物という点前の名前の通り、今回のメインは唐物の扱いになります。
唐物の清め方や置き方などの稽古をします。
お茶は濃茶になるので、楽茶碗を使うことになります。
濃茶ということは、途中で問答があります。事前に濃茶の銘を調べておくと安心ですね。
茶杓は、節が下端にある元節を使います。
象牙ではないので注意しましょう!
象牙の茶杓を使うのは、台天目と盆点の点前になります。
次に建水ですが、濃茶の場合はほとんど唐金になります。
唐物も同じように唐金建水を使います。
【四ヶ伝】唐物(風炉)の点前のポイントまとめ!
四ヶ伝の唐物(風炉)の点前のポイントはいくつもあります。
今回は中でも重要なものを下にまとめました。
【ポイント】
- 唐物を清めるとき帛紗は「真」
- 唐物を拝見に出すとき帛紗は「行」
- 拝見に道具を出すときは茶杓の上に仕覆の紐をかける
- 唐物を拝見に出すときは鐶付
- お菓子は3種
- 膝行と膝退がある
- 茶筅はきれいなときは建水の肩
- お茶はすくいだしのみ
唐物の扱い方を稽古しているので、帛紗のさばき方を覚えるのが大変かもしれません。
清めるときは「真」で拝見のときは「行」と覚えておくと少しは迷わないかと思います。
点前の中で膝行と膝退があるので、稽古中に自分の座る位置や道具の置き場所を考えながらするのがおすすめです♪
【四ヶ伝】点前のときの服装は?
小習よりも四ヶ伝はレベルが上がったお点前に感じるかと思います。
稽古場によっては、「そろそろ着物でお稽古をしましょう」という場合もあるのです。
茶事のときには着物で点前をするので、お稽古のときから着物でしていると妙な緊張感にならず安心です。
やはり洋服とお着物では動き方が変わります。
気持ちの中でも普段と違うお着物で点前をするだけで不安になることもあります。
お着物の種類は、色無地や小紋かと思いますが、稽古場の先生や先輩に相談するのが無難です。
「着付けができない」「久しぶりで着れるか不安」という場合は、無料で着付け体験ができる教室へいくのも良いでしょう。
茶道をする上で着物は必ず必要になってきます。
四ヶ伝に上がったタイミングで着付けを覚えてしまうのも今後特に役立つと思います。
着付け教室は、費用をできるだけ抑えたい方は、体験レッスンや受講が無料の「日本和装」がおすすめです。
>>>日本和装の公式サイトを見てみる
ただし、日本和装は体験レッスンや受講料は無料ですが、勉強会&販売会があります。
販売会は不安という方は、体験レッスンが無料、受講料が1回500円(税込)から始められる「いち瑠」も利用しやすいです。
>>>通い続けたい着付け教室No.1 きもの着方教室いち瑠の公式サイトを見てみる

私も茶道を始めたばかりの頃は、YouTube動画を見ながら独学で着付けていました。
しかし、独学なので、自分のその日の体調や選んだ着物や帯によって上手くできる日とできない日があったのです。
着付けの方も茶道と同じくしっかり先生に習うことで、できるようになりました。
お茶会へ参加するとき、茶事の裏方になったときなどに困らないよう着付けもできるようになっておくと便利ですよ。
【四ヶ伝】唐物(風炉)の準備や点前のまとめ
- 四ヶ伝の1つである唐物(風炉)で準備するものは主に6つ
- 曲水指は事前に濡らしておく
- 楽茶碗を使う
- 事前に濃茶の銘を調べておくと安心
- 茶杓は、節が下端にある元節を使う
- 清めるときは「真」で拝見のときは「行」
- 膝行と膝退がある
四ヶ伝の唐物(風炉)は、ポイントをおさえて点前を進めていきましょう!
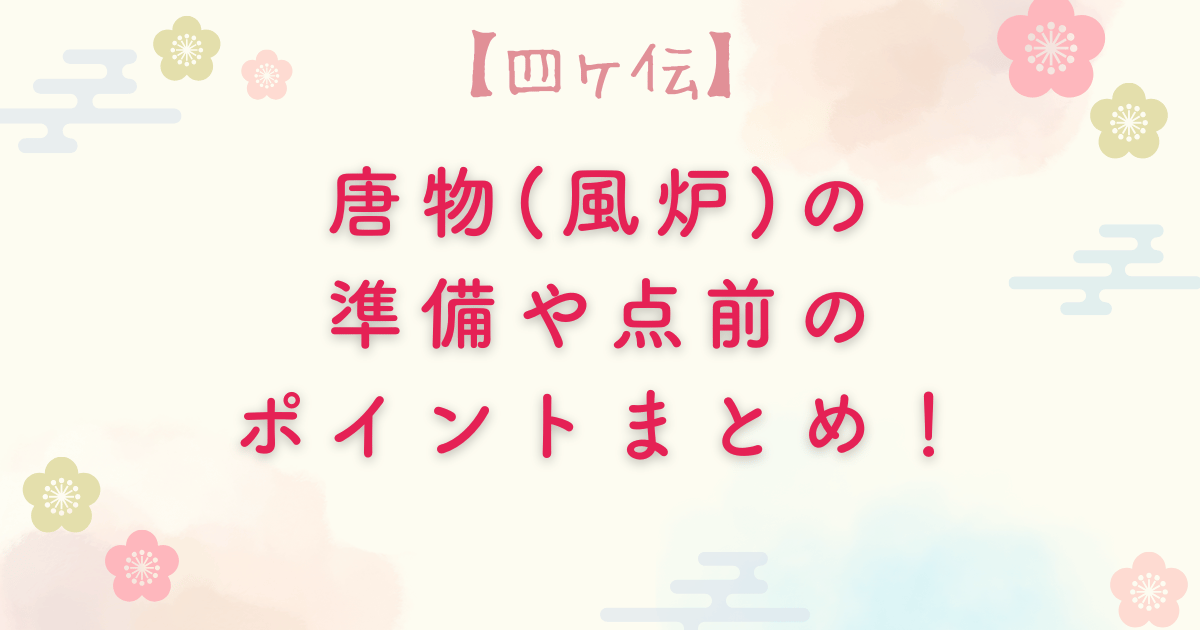




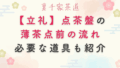

コメント